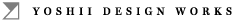December 2010
民族の壁
「1945年12月25日、太陽がすっかり沈み、これで本当に台湾島が見えなくなった。」こんな手紙のナレーションで始まる台湾映画「海角7号」。DVDを借りる前に、この映画を全く知らなかった私は、途中の軽いコメディタッチに選択を間違ったかなという思いが頭をよぎったが、見終わったら一瞬でもそう感じた自分が許せないほど良い映画だった。映画は、台湾に赴任していた日本人教師が、敗戦により日本へ帰還する船のシーンから始まる。日本が統治していた台湾との関係がベースで、台湾に残した恋人に綴った7通のラブレターと現代が交錯してストーリーは展開する。
中国との関係はしっくりこないが、台湾との関係は違う。台湾の現、馬政権はかなり中国寄りらしいが、それでも台湾という国の人々は、嬉しいことにかなり日本人には好意的だ。反対に、中国との関係は特に尖閣諸島の衝突事件からかなり深刻な局面にある。マスコミは日本の損ばかりを強調するが、日本人が中国人に対し嫌悪感を抱きつつあることの方が問題だと感じるのは私だけだろうか。
さて、映画に戻るが小島友子という日本名を持つ台湾の教え子と恋をした日本人教師。敗戦により、二人の恋は成就することなく終わる。「海角七号」とは、恋人小島友子の日本統治時代の住所だが、日本に帰った教師の娘が、父親の死後この古い手紙を発見し台湾に送る。しかし、日本統治時代の「海角七号」という住所は忘れ去られ、郵便物は宛先不明で届けられずにいる。果たして手紙は届くのか。
「海は、希望と絶望の両極端にある」。これは、手紙に綴られた文章だ。平和を切望すれば手に入れられる現代、世界は海で仕切られているのではなく、海によって繋がっていると思わせてくれる1本だ。中国では日本統治時代を美化しているという理由で、公開までに少し時間がかかったそうだが、台湾の人達は南国気質で笑い飛ばしたという。本当に愛された映画らしく、台湾映画では歴代トップの興行成績を記録している。
この映画のヒットを知って、台湾との友好関係をとても嬉しく思っていた矢先、朝日新聞で1930年10月に台湾中部の霧社地域で起こった「霧社事件」という抗日事件を知った。記事には生き残った日本人女性の証言が掲載されており、その内容は衝撃的だった。タイヤル族という先住民が日本の統治に反発し、小学校で地元民との運動会を開催中の日本人を襲撃。134人の日本人が殺されている。女性は当時小学生で運動会に母と妹と出掛け、事件にあい鼻先を刀がかすめながらも、母とともに逃げ、一昼夜身を潜めかろうじて助かったという。しかし、この事件で妹は殺され、警官だった父親も殺されている。その後、日本に戻ってからは、決して事件のことは口にしなかったと記事にはあった。友好関係で包まれたような台湾との間にも、この様な歴史が存在したのだ。果たして民族とは何を持って結びついているのだろうか。そして、その民族が成熟した国を成すには、どれだけの時間が必要なのか。
「海角7号」という映画の中でも、日本人教師が「貧しい教師の僕が、どうして民族の罪を背負えようか」と、日本に連れて帰れない恋人に許しを乞う。民族という見えない壁と愛という力によって容易に乗り越えられる壁が時代を経て静かに交錯する。詳しいストーリーは省いているので、DVDを観ても楽しめる筈。お正月休みには、是非この台湾映画の鑑賞をお奨めしたい。
株式会社ヨシイ・デザインワークス 吉井純起
November 2010
リーダーの存在意義
中国広州で開かれているアジア大会。中国とは、人口が違うので金メダルの数で圧倒されるのは仕方ないが、人口の少ない韓国にも差をつけられている日本は情けない限りだ。蓮舫議員の「二位じゃいけないのですか」の言葉どおり、日本には「銀」が多いのが何故か悲しい。まぁ、ロンドンオリンピックを見据えての前哨戦ということで、選手強化の課題発見と考えればいいのだろうが、去年の事業仕分けでは日本オリンピック委員会(JOC)の選手強化費を含むスポーツ予算は削減と判定されたが、その後どうなったのだろう。今回のアジア大会の結果から推測すると、きっと削減されたのだろうと勘ぐりたくなる。なんだか、国民の士気まで仕分けられそうだ。
それにしても、相変わらず中国は巨大で強気である。最近の傍若無人ぶりは目にあまるが、対する日本の弱腰の外交姿勢には怒りさえ感じる。菅総理は、横浜で開催されたAPECで、議長国としてリーダーシップを発揮したかったのだろうが、恒例である開催国の民族衣装を着ることさえ実現できなかった。拒否されたのか、気を使ったのかは定かでないが、象徴のような記念撮影を日本が断ち切ってしまった。様々な歴史や国益の壁を乗り越えて、開催国の民族衣装を着るという行為こそが国際会議の意義でもあるはずだ。実は尖閣諸島周辺海域で起きた海上保安庁の巡視船に対する中国漁船の体当たり映像を公開しなかったのも、中国の参加を仰ぐためだったと言われている。そうまでして漕ぎ着けた胡錦涛国家主席との会談であったが、テレビに映し出された菅総理の原稿を読む姿は国民、いや世界中から頼りない総理として記憶されたことだろう。テレビ番組でリーダーシップのリーダーではなく、朗読者という意味のリーダーだと皮肉られていた。うまいうまいと拍手を送る私自身の姿を振り返って、自国の総理大臣を素直に尊敬できなくなった日本を憂うこの頃である。
私はリーダーシップは、個人が備えている資質であるが、作られるものでもあると考える。民主党内には、あまりに多様な意見が存在し、菅総理が輝ける舞台は整えられないし、サポートする人材も少ない。自衛隊を暴力装置と表現した仙谷官房長官も然り。菅総理の女房役どころか、仙谷総理大臣と揶揄されている。就任時に輝いていた菅総理の顔は、30%の支持率を切った今となっては見る影もない。今こそ、リーダーとしての存在意義が問われている。
このまま民主党政権が続くと、中国やロシア、アメリカとの関係はどうなるのか。すべては日本の安全保障の根幹を成す日米同盟が揺らいだ結果だが、木を見て森を見ることができない未熟な民主党政権に国の安全を委ねられないのは確かだ。日本国民は国防を政治家や官僚に委ね、自ら考えることを拒否してきたが、幸か不幸か「国」としての有り様に向き合う機会を現在突きつけられている。私の頭の中では、尖閣諸島を国有化して、陸・海の自衛隊を駐屯させろとか、勝手に頭の中で妄想している。もしかして、それができないのは政府が怯える何かが起こり得るということなのか。はっきりしない外交問題に、ためらい続ける政府が歯痒いばかりだ。とりあえず、今週末から仕事で大連に行くので、民間レベルでの日中友好を深めてまいります。まずは理解からということで。
株式会社ヨシイ・デザインワークス 吉井純起
September 2010
虫の音は雑音?
ようやく酷暑の夏が終わり、夜には涼やかな虫の音が聞こえるようになった。清少納言は枕草子で「春はあけぼの」と四季の移ろいを讃えたが、他の季節は何だったかなと、遥かな記憶を巡らせてみる。そうそう、「夏は夜」で「秋は夕暮」だ。しかし、さすがの清少納言も現代の真夏の夜をイメージできないだろう。クーラーの室外機の音と24時間眠らない街の明かり。ろうそくの揺れる炎や月光だけで照らされる風景など、停電やキャンプでもなければありえない。とはいえ、昔には戻れないのだ。ただ、失ってはいけないものがある。日本人の持つ情緒感だ。何を今さらと笑われそうだが、地域に於いても、日本というカテゴリーで考えても、この心を表現することが今は大きな強みとなる。
私はグラフィックデザイナーという職業柄、商品開発や地域の特産品開発に携わる機会が多い。効率が重視された時代が終わっていることは、誰しもが気付いている。しかし、昔のようにお金をかけて表現できる時代も終焉したし、過剰包装を否定するエコデザインも上げ潮だ。最近の安い中国製品が氾濫する市場で、どうやって日本製品が勝ち残るかは喫緊の課題である。
私のところにも、新たなデザインを導入することで、安価な粗雑品と競うことから離脱したい。そのために付加価値を付けたいとの相談がある。確かに、製品やサービスなどが、本来保有する実力だけで戦うことは難しい時代だ。更に、今あるモノに唯一無二の価値を見いだす創造は至難の業といえる。ならば、消費者が期待するものと、企業が提供するものとが、より高い位置で均衡が保たれた状態を創り出す方策が求められる。そこに「満足」という付加価値が存在するからだ。
この「満足」を生み出すのに必要な要素が、私は「情緒感」だと考えている。文頭に涼やかな虫の音と書いたが、東京医科歯科大学の角田教授が、「虫の音」を日本人は「虫の声」として言語脳と呼ばれる左脳で受け止め、西洋人は雑音として右脳で聞いていると説明している。虫の音を聞いて、もう秋だなぁと感傷に浸れるのは日本人だからなのだ。
私がデザインで心掛けるのが、この感覚を持ち得ている日本人の「心の琴線にふれること」だ。絵や写真、言葉でストレートに表現しなくても、感じ取る能力を備えた日本人は五感で感じ取ってくれると信じている。だから、足し算だけでなく、引き算もデザインには必要なのだ。
さて、最近はイメージキャラクターやシンボルマークなど、地域や団体が広く公募する機会が目立つが、それがもたらす功罪が気にかかっている。イメージアップではなく、逆にイメージダウンにもなり得ると危惧しているからだ。それは、制作者側の問題ではなく、選考者側にシステムの問題があると考える。「虫の音」を「虫の声」として聞くか、雑音として聞くかは、育った言語環境によって左右される。シンボルマークやイメージキャラクターだって、価値を高めるという覚悟や意識がないと、大きな負の財産を背負わされることになるということだ。安易な公募はご用心、ご用心。
株式会社ヨシイ・デザインワークス 吉井純起
July 2010
岡ちゃん、ごめんね。
全くといっていい程期待が持てなかったワールドカップサッカーだったが、ふたを開けてびっくりだ。日本チームの意外なまでの頑張りに、心躍らせる幸せな日が続いた。試合当日は、仕事を調整しながら、時間配分に気を配り、夕食メニューまでチェックした。都会ならスポーツバーに行きたいところだが、残念なことに我家が観戦会場だ。サポーターは妻と私の二人のみ。サッカーには素人の私たちだが、スポーツ観戦には熱くなる。闘うデザイナーは仕事はもちろん、勝負事となると俄然熱くなる。
しかし、カメルーンに勝てるなんて予想外だった。「岡ちゃん、ごめんね」は、ネットに書き込まれていたサポーターの言葉だが、私も同じくつぶやいた。「岡ちゃん、ごめんね」と。
サムライブルーのユニフォームを身につけた選手たちは、まさに侍であった。DFの闘莉王選手は日本人よりも日本人らしい。常に真剣を腰にさしているようなピリピリとした緊張感と威圧感を放ち続けていた。長友選手は、ユニフォームのデザインから、たすきを掛けた討ち入りの装束を想像した。無尽蔵のスタミナをもってのしつこいプレーにぞっこんだ。翌日、鏡の前の私に妻が、「長友と同じ身長、体重はマイナス4
キロ。なのにこのウエストの横の肉は何? 」とつぶやく。確かに、長友選手にこのたるみはない。同じ肉でも、種類が違うのだ。
もうひとりのお気に入りは松井選手だ。ずっと、松井選手をなぜ使わないのかと、私の中で不満がくすぶり続けていたが、今回の起用で溜飲が下がった。しなやかな動きに洗練されたエスプリが漂う。海外は人を成長させるなぁと、なぜか上から目線の文章に恥ずかしい限りだが、日本中が、監督でコーチで家族の気分だった。
さて、頑張った選手を称えながらも、いつも頭のどこかで背番号1 0
を背負った中村俊輔選手を探していた。画面の端に映る中村選手が笑っていても心の奥底を探ってしまう。きっとチームが勝っても心底称える気持ちにはならなかっただろう。私もベテランと言われる年齢になり、ついつい中村選手の姿に自分を投影してしまう。だから、今大会で輝きを放った金髪のニューヒーロー本田選手に対し、無条件に拍手喝采は贈れない。中村選手に対する判官贔屓もあるのだろう。ビックマウスに抵抗を感じるし、サングラスでカッコ良く帰って来た姿もなぜか気に入らない。保守的と言われようと日本人の私は肌触りの悪さを感じ取り、「世の中そんなに甘くはないぞ」と冷ややかなエールを贈っている。
確かに新旧交代は世の常だが、世界が見守る中での屈辱的な交代劇は中村選手にとってあまりにも残酷だった。ピッチの上は昔のひ弱な残像に支配されたままだ。このまま引退という幕引きはない。次回のワールドカップのピッチには立つことは難しいだろうが、それでもまだまだ途上である。頂上は自分で決めることができるし、そこには大会で無念を刻んだ自身の心への許しが存在するはずだ。今後自分自身とどう向き合い、どう奮い立たせるのか、中村選手の奮起が気になるところだ。俊輔、ペテランの意地を見せてやれ。ここでの踏ん張りが日本サッカー界の発展へと繋がる。
株式会社ヨシイ・デザインワークス 吉井純起
April 2010
九寨溝旅行記~其の2
政局は混乱が続き、一向に出口の見えない日本だが、少々節約にも飽きてきた。小さな贅沢をしたいと、気持ちは解放を求めている。特に今は、ゴールデンウィークをどう過ごすかとウズウズしている。中国好きの私には、上海万博を人参としてぶら下げた大国の手招きが見えるのだが、万博にはあまり興味がない。しかし、中国が万博に向けた取り組みには大変興味をそそられる。例えば、パジャマで街を歩かないとか、列には整然と並ばなければならないとか、うまく市民に浸透したのだろうか。
さて、九寨溝旅行記というタイトルをつけたからには、旅行記の続きである。前回は成都を経由して世界遺産の九寨溝を訪れた所で終わってしまった。只々青い空と山々に囲まれた黄龍・九寨溝空港に着き、九寨溝へはバスで向かう。美しい山々、その裾野にはヤクの群れが車窓から見える。五体投地で聖地を目指すチベット族の人たちとも出会う道である。水の流れが一層激しさを増してくると、いよいよ九寨溝付近だ。九寨溝は環境に配慮した専用バスで巡る。ここ九寨溝は静かな湖面と激しい水の流れが緑の中に混在している。その激しい水の流れに木々が育っているから、まったく不思議な光景が造形されている。林の中を激しい川が流れているようなもので、日本では絶対にみられない光景だ。そして、様々な青色に出会える地である。
私が一番美しいと感じたのは、エメラルドグリーンに輝く蒼き「五花海」という湖である。特に真冬の早朝に訪れたこともあって静寂が支配している。この世の風景ではないようだ。遠くには眠山山脈、周りは豊かな緑に囲まれ、朝霧に包まれた湖から水蒸気がゆっくりと静かに立ち昇る。神秘的で、湖底にはまるで龍が息を潜めているようだ。ちょっと現実的に伝えると、巨大な弁天池(秋芳)と言っていい。あの色は不思議だったが、なるほど石灰分が多いという共通項が同じ色を形成するのか。疑問が解けた。しかし、中国という国は幾度訪れても、次から次へと興味が沸く。自然や歴史が作り出す感動には悔しいことに日本はかなわないだろう。チベット族の可愛いバスガイドさんとも名残りおしく、またまた中国にぞっこんとなったが、夜のショーでは観客が少ないという理由で暖房を入れてもらえなかった。広く立派な劇場で寒さに震えながら、素晴らしいショーを見るなんて、どこかおかしい。あと、四川省を訪れるなら、是非世界一の大きさを誇る楽山大仏もおすすめだ。川から岩に掘られた高さ7
1 m のどこかユーモラスな大仏を見上げる。この日は元旦だったが、合掌することを忘れさせる程の圧倒的スケールだった。
実はこの原稿を書いている日も中国大連から帰国したばかりだ。観光を超えて、ビジネス面で切り込みたいという思いは募るばかりだが、今回は異質の国民性に跳ね返される結果となった。織り込み済みとは云え、手強い。この国には九寨溝とは異なる豊かさを求める欲が濁流となって流れている。果たして、華僑ならぬ和僑として濁流に飛び込むことが許される日は来るのだろうか。
株式会社ヨシイ・デザインワークス 吉井純起
February 2010
九寨溝旅行記~其の1
働いていると、長期の休みにはどこに行こうかとウズウズし始める。芭蕉が「奥の細道」で『そぞろ神の物につきて』と記しているのは、こういう心境なのだと勝手に同レベルに考えている。ということで、中国の道祖神の招きにあったことにして、正月の休みは四川省にある「九寨溝(きゅうさいこう)」を目指した。
「九寨溝」は世界遺産である。チベット族の9つの集落(寨)があったことから名付けられたこの美しい秘境の地は、注目の観光地だ。まずは福岡空港から上海、そして中国の国内線に乗り継ぎ3時間半、人口1,200万人を擁す四川省の省都「成都」に着く。上海に比べると、まだまだあか抜けないが大都会である。この「成都」は2,300年の歴史を持つ三国志の舞台となった古都で、劉備玄徳、諸葛孔明らが活躍した胸躍る街だ。表現が稚拙だが『凄い所に来た』と、歴史や物語の中の一部に直接入り込んだ喜びが溢れる。
さて、九寨溝へは、ここから更に飛行機を乗り継がなければならない。ということで、初日は、成都泊まりである。しかし、翌朝はどんよりとした曇り空。視界が悪い。飛行機は飛ぶかなと不安になっていたら、現地ガイドが開口一番「今日はいい天気ですね」と挨拶。ここ成都は盆地に位置するため、一年中こういう天気らしいが、地形的なものだけでなく、公害も影響しているだろうと勘ぐりたくなる。この地域では太陽光発電は無理だなと、ちょっと日本が優位に立った気がして小さくガッツポーズした。しかし、「成都」の人口が東京都並みであることを思いだして、私の前に巨大な中国が立ちはだかる。やはり、大国中国を受け入れるしかないのか。そんなことを自問しながら、今日はいよいよ「九寨溝」を目指す。
飛行機が成都空港を飛び立ち、厚い雲を抜けると驚くほどの青空が拡がった。日本では観ることの出来ない空の色だ。目指す「九寨黄龍空港」は、高度3500m、富士山の頂上に匹敵する高地にある。その為、飛行機は岷山山脈の峰々の間を縫うようにして空港を目指すが、着陸は天候に左右されることが多く、私たちの場合もそろそろ着陸かと思う間もなく、成都空港に引き返すことになった。再フライトで無事に到着した「九寨黄龍空港」は只々青い空と遠くの山々に囲まれ、大感動である。しかし、さすがに空気が薄く、ツアーで一緒になった方は飛行場に降り立ち数メートルを歩くだけでいつもと違う息切れを感じると言っておられた。年齢や体質、当日の体調によっては、具合が悪くなる場合があるらしい。これから、九寨溝・黄龍に行こうと思っている人は用心が必要だ。
今回のツアー参加者は私たち夫婦を入れて総勢5名。寒い時期に高地を目指すのは時間が限られている会社勤めの人だろうと思っていたら、後の3名の方々は驚くことに何れも70歳を超えた男性で最高齢は82歳。高地を甘く観ていたと、身体的な息苦しさがあったらしいが、製薬や医療関係の仕事ということで、流石に薬の用意は万全、旅慣れた強者3名に脱帽である。明るく、年齢を感じさせない好奇心と行動力に、日本が高度成長を遂げる原動力となった自信が感じられ、衰えることのない好奇心を持っているということは、人生の輝きを増すものだと、実に身になる旅の出会いであった。
さて、オフシーズンの冬の九寨溝。入場料も格安だ。エメラルドグリーンの湖が悔しいことに素晴らしい。中国の勝ちが高らかに宣言された。詳しくは、次回で。
株式会社ヨシイ・デザインワークス 吉井純起
January 2010, NewYear
映画「2012」に観る世界の国力図
「2012」という映画を観た。この映画には2012年、地殻変動によって世界終末へと向かう人類の危機が描かれているが、CGを駆使したリアリティ溢れる映像は迫力満点で、さすがハリウッドと唸りたくなる仕上がりだった。
しかし、何より驚きだったのが、映画に描かれている2012年における世界の国力の構図である。あながち映画の中の出来事と安易に片づけられない内容で、世界終末が予測される中、秘密裡に現代版「ノアの箱船」といえる巨大船が建造されるのだが、その建造を委ねられた国は中国であった。現在のメイド・イン・チャイナにはまだまだ疑問符がつくが、「世界の工場」としての地位はさらに増幅し、そこに世界最高峰の技術が追いつき技術大国の地位を確立しているということか。また、この地殻変動にいち早く気付いた地質学者はインド人だった。これまた世界の頭脳と呼ばれつつあるインドパワーが現実のものとして描かれている。ところで気になるのは日本の存在だが、残念ながら台頭するアジアの途上国と比較して存在感は皆無だった。
そこで思い出したのが、「21世紀は国のモチベーションの総量が国力に比例する」という元山口大学学長の広中平祐氏の言葉である。事業仕分け作業で、科学技術分野の予算の凍結や縮小が問題となり、ノーベル賞受賞者の野依良治氏が「君たちは歴史という法廷に立つ覚悟はあるのか」と言葉を投げつけたが、確かに日本はこのままでは危うい。アジアが世界の中心となりつつある今、日本が取り残されていく焦燥感に包まれた2010年初頭である。
株式会社ヨシイ・デザインワークス 吉井純起